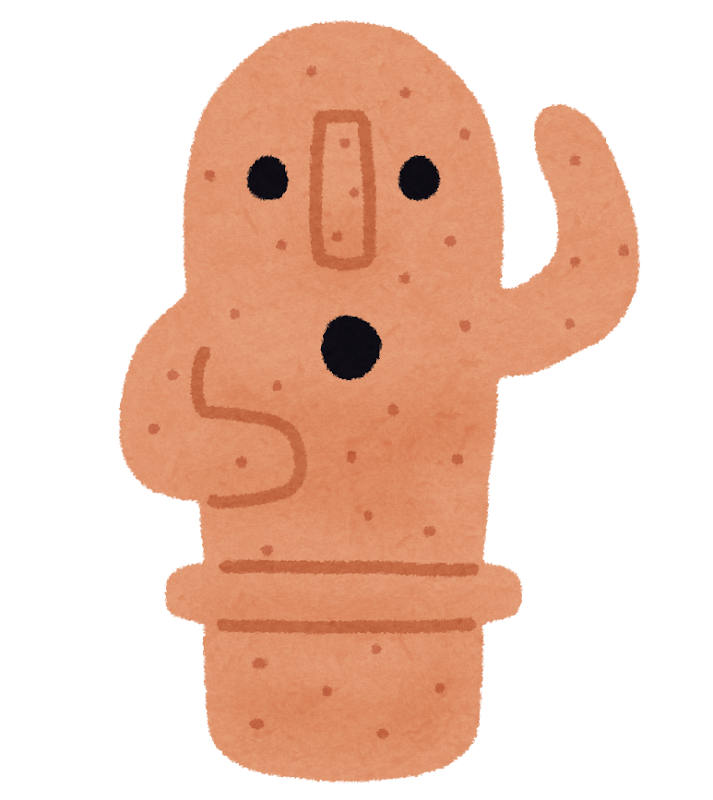結婚するまで雅楽とは全く縁はなかったのですが、家内が楽家の出身という縁で雅楽に興味を持つようになり、八王子文芸アカデミーで古事記や万葉集等を受けてみたいと思うきっかけにもなりました。
(1)雅楽とは?
雅楽は宮廷のさまざまな儀式や遊興の音楽として千三百年以上にわたり伝承されてきました。雅楽には大きく分けて次の三種類があります。①国振歌舞(神楽、東遊、久米舞等)②大陸系の楽舞は中国大陸系の唐楽(管絃と舞楽)、朝鮮半島系の高麗楽③平安の歌曲(和歌による催場楽、漢詩による朗詠)があります。
(2)歴史・文学に見る雅楽について
「古事記」には大国主が須勢理毗売を連れて黄泉の国から脱出する際、琴が樹にぶつかって大きな音をたてたと記されています。天宇受売命の神がかりの舞や天皇の儀礼で行われた游部の呪術的な所作、海幸・山幸神話で語られる隼人舞や吉野の山びとの国栖奏など、宮廷の祭りの庭で演ずるものや服属の意味をもって奏上するものもあります。大宝令以前は宮廷の「雅楽寮」においては、高麗・百済・新羅の三国楽や東楽、度羅舞、伎楽など外来の楽舞が伝授され在来の日本的楽舞である久米舞・五節舞・田舞・倭舞なども雑楽と呼ばれて、国家によって管理されていました。
「万葉集」の巻一には、宮廷儀礼や行幸・饗宴にかかる歌が収められ,それらは宮廷を祝福賛美する心に支えられた讃歌を中心にしております。万葉集での古事記歌謡は一首(巻二・90)が引用され,万葉集に搭載された二首の「古歌」(1009・1010)はトヨノアカリ(豊明節会)の大嘗祭の後日に豊楽殿で催される宴の和琴の伴奏で唱和されたと思われます。
「平家物語」の敦盛の最期の段で横笛「小枝」という一管、小督の段では琴の音と楽は想夫恋。「枕草子」のひくものは…の段で清少納言は琵琶が一番と語っています。「徒然草」にも天王寺の舞楽、特に雅楽の場面が多く出てくるのは「源氏物語」で若菜・下の巻では六条院の女楽、鈴虫では横笛を奏でる夕霧、明石の巻では琵琶,乙女の巻では琵琶の音色を述べています。平安時代の文学作品には雅楽に関する逸話が多くみられます。
文学を勉強しながら雅楽を愛でて平安の昔にタイムスリップ出来たらと思います。
最後に宮内庁式部雅楽部では年1回、一般の人が雅楽を鑑賞できる機会があります。(秋季特別演奏会)毎年六月下旬から七月にかけて開催日時や演目、申し込み要領などが発表されます。鑑賞は無料ですが、抽選での申込みとなっており、狭き門になっております。楽部の楽人が日夜研鑽している場で伝統の雅楽が見られるという貴重な機会ですが、コロナ禍で本年度は開催されるかは分かりません。早く、コロナが収集したらいいですね。
(受講生 S.N)
八王子文芸アカデミー
文芸の楽しさをご一緒に味わってみましょう