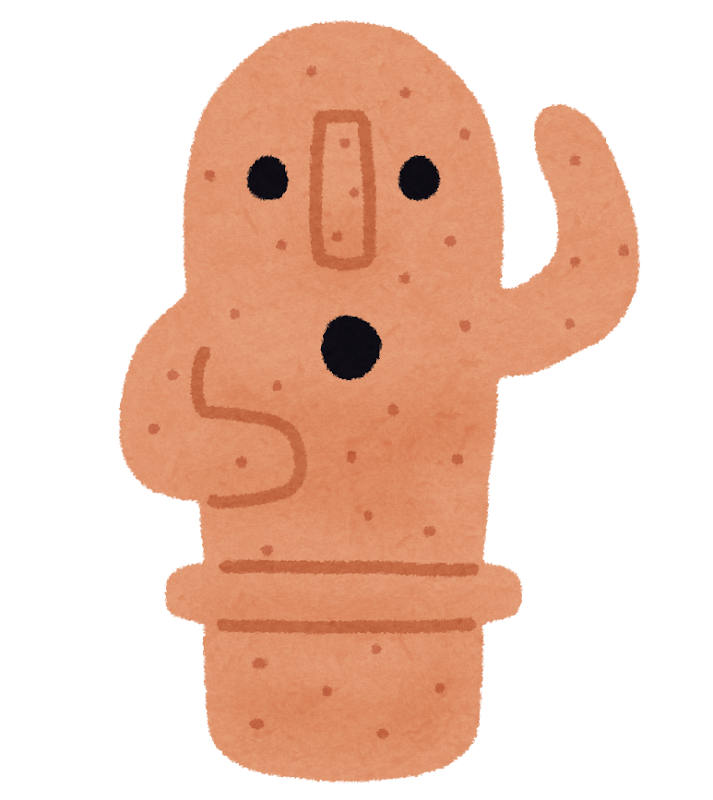NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を毎回欠かさず見ています。最初は誰が誰だかよくわからず混乱しましたし、現在も「13人」全員の名前と顔(ドラマ上の)がわかるようなわからないような、という状態ではありますが、それでも面白く見ています。三谷幸喜が作るドラマが面白く、『吾妻鏡』が面白く、それぞれの俳優の演技や色が面白い、色んな相乗効果が面白いのでしょうが、個人的には、鎌倉の向こう側の「京の都」の貴族たちの動向、ドラマにはほとんど描かれていない文学に思いをはせることもあわせて楽しんでいます。
1192年頼朝が征夷大将軍となり、死去後その子頼家が家督を継ぐ(1199年)のですが、その頃、都では藤原俊成が、歌人として最も活躍した時期でもありました。1194年ころ、俊成が判者(和歌の勝ち負けを決め、その理由を述べる役割)をつとめた『六百番歌合』(藤原良経主催)は、新派御子左家(寂蓮・定家など)と由緒ある歌学の家六条藤家(顕昭・季経など)のほか、主催者一族良経、慈円など12人の当代の歌人たちが一人百首ずつ和歌を提出し、六百番1200首の文芸史上に残る大歌合となりました。中でも、「紫式部、歌詠みの程よりも物書く筆は殊勝なり。その上、花の宴の巻は、殊に艶なるものなり。源氏見ざる歌詠みは遺恨のことなり」(13番 枯野)という名判詞は、後世にも大きな影響を与えました。物語作者としての紫式部への評価、歌人にとって『源氏物語』が必読の書であるという提言は、その子藤原定家をはじめ、ひとびとに受け継がれてゆきます。一方で、判者であった俊成は御子左家側の歌人でもあったため、歌合の判を不服とした顕昭によって『六百番陳状』という、俊成判への批判や不満を書いた書も作られました。鎌倉では武士が武力で戦っていましたが、都の貴族たちは和歌で争っていたわけです。
俊成がドラマに登場することはないようですが、第3代鎌倉殿(実朝)は、定家(俊成の子)に師事し、歌人としても名を残しました。『新古今集』に熱意を注ぎ、和歌の力で日本を統べようとした後鳥羽院、和歌を習い、後鳥羽院や定家と繋がろうとした実朝がどう描かれるのか、これから楽しみです。
※歌合(うたあわせ)…左と右にわかれた二グループから一首ずつ歌を出して、二首一番の組をつくり、それぞれの番に勝ち負けをつける文学的遊戯。9世紀後半には行われている。
(岡田ひろみ)
八王子文芸アカデミー
文芸の楽しさをご一緒に味わってみましょう