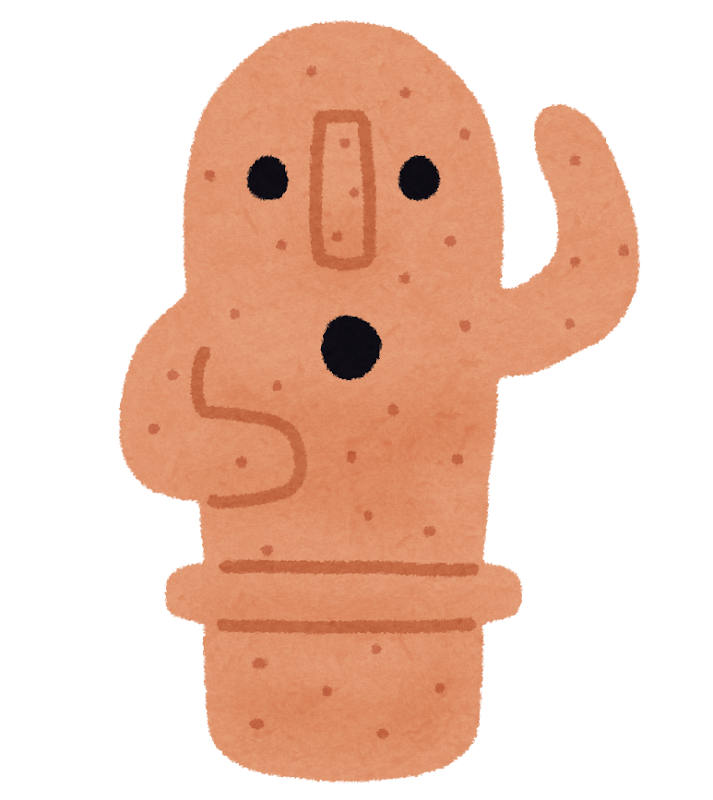「平家物語を読む」の第3回と4回の間に数日パリに飛んだ。「日本芸能史研究の新地平」というワークショップで話すためだ。3時間ほど出発が遅れたJALで正午過ぎに離陸。日本とパリでは8時間の時差があるが、発表は翌日の午前中。時差ボケしてはいられないので、すぐに時計をパリ時間に合わせて、なるべく寝ないで過ごす作戦である。
機体は夜時間を飛ぶ。周りが殆ど寝ている中でインド映画を見ていたら、CAさんが「オーロラが見えてます」と耳打ちしてくれた。オ、オーロラ?ここはどこ?現在、ロシア上空は飛べないので、パリに行くのに、太平洋を北へアラスカ、カナダの北部からグリーンランドを抜け、アイスランドに降りイギリスを横断してフランスというルートをとる。15時間半の行程である。
あわてて窓からのぞくと、巨大な白い柔らかな質感のカーテンが、ドレープを作ってはるか上空から静かに垂れている。地上から見上げるオーロラは、紫や赤・緑の色に光りつつ次々に姿を変えるイメージだが、飛行機の窓外のオーロラは、オパールのような白一色で、その形も見る間に変わるのではなく、気がつくと変形している程度に動きは少ない。オーロラの向こうの空には漆黒の天に星が果てしなく輝き、飛行機の翼がオーロラをかきわけるように、もどかしく進むさまを、私は窓にへばりついて40分程ずっと眺めていた。
この度のワークショップの責任者N大のT教授はパリに一足先に発ったが、着いて具合が悪いから休むとホテルの部屋に入り、そのまま亡くなって発見された。58歳。彼の遺志を尊重してやり遂げようという事になって、私は予定通りパリに向かったのだ。人は死ぬと魂はどこへでも行けるのか。たとえばこの大気圏のオーロラの中にも?ゆっくり静かに変化し続けるオーロラの淵にも。
後で聞くとちょうどアラスカから北極海にかかる地点で、「普通は見えませんし、出ても数分とか小さくて、先ほどのように長時間続く大きなオーロラは私達も初めてです」とCAさんも興奮気味に語っていた。オーロラは日本語では「極光」。古典文学には存在しない光である。
(菅野扶美)
八王子文芸アカデミー
文芸の楽しさをご一緒に味わってみましょう