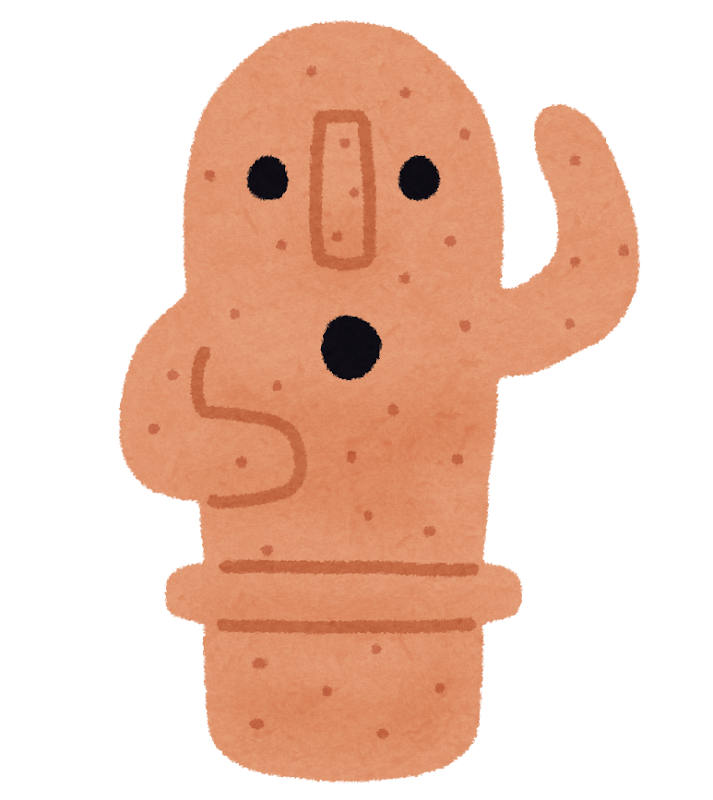青木繁の「わだつみのいろこの宮」を見たのが古事記を読むきっかけとなった。周知の通り、山幸彦が兄の海幸彦に借りた釣り針を探しに海神の宮を訪ねる。塩椎神に教えられた通り宮の門前の高木に上っている絵で、その高木がカツラだった。カツラは好きな樹だ。
カツラは日本の名木である。カツラ料カツラ属で三種からなる。すぐれた材は多くの仏像彫刻に、ハート形の葉は新緑が美しく葵祭に、使われる。秋の黄葉からはキャラメルを焦がしたような甘い香りが漂う。古代、カツラは霊木と見做されていた。「古事記の森」にはカツラ以外にどんな木があるのか、趣味である「樹木ウォッチング」を思い立った。しかしながら、古事記の森には「古文」という難関がある。多くの現代語訳本の中で三浦佑之の『口語訳古事記』が最良のガイドブックとなった。さらに、共立アカデミーの公開講座に「古事記」があることを知り、受講することにした。受講が愉しく面白いのは成績とは無縁だから。
古事記の森には約50種の樹木があり、多くは西日本に自生し、渡来種はほとんどない。かしは(カシワ)、くぬぎ(クヌギ)、ひひらぎ(ヒイラギ)など現在と同じ掛名も少なくないが、「あぢまさ」、「さしぶ」、「みつながしは」など、古名の同定には『古語植物辞典』に頼らざるを得ない。「さきくさ」「たちそば」など、現在の名は何か、諸説あり、定説のないものもある。
仁徳天皇の条に出てくる「あぢまさ」とはヤシ科の「ビロウ」のこと。九州南部、沖縄に自生する。宮崎の青島神社には天然記念物に指定されたビロウの林がある。沖縄では「クバ」とよばれ、御嶽に植栽し霊木とされる。葉でクバガサ(笠)やクバオージ(団扇)などが作られる。霊性と実用性を併せ持つ木である。平安時代の高級牛車の屋根はビロウの葉で葺かれ「檳榔毛車」と呼ばれた。「あぢまさの語源」の一説に、新芽が食用になり「味勝る(あじまさる→アジマサ)」という俗説があるが、そんな発見も古事記を読む愉しみの一つだ。
古事記を読むこと十数年、それでも覚えられない多くの神々や禁断の恋、嫉妬、裏切り、謀略など複雑極まる人間、それに点景を添える草木など古事記は魅力溢れる書である。
(受講生 関口晃)
八王子文芸アカデミー
文芸の楽しさをご一緒に味わってみましょう