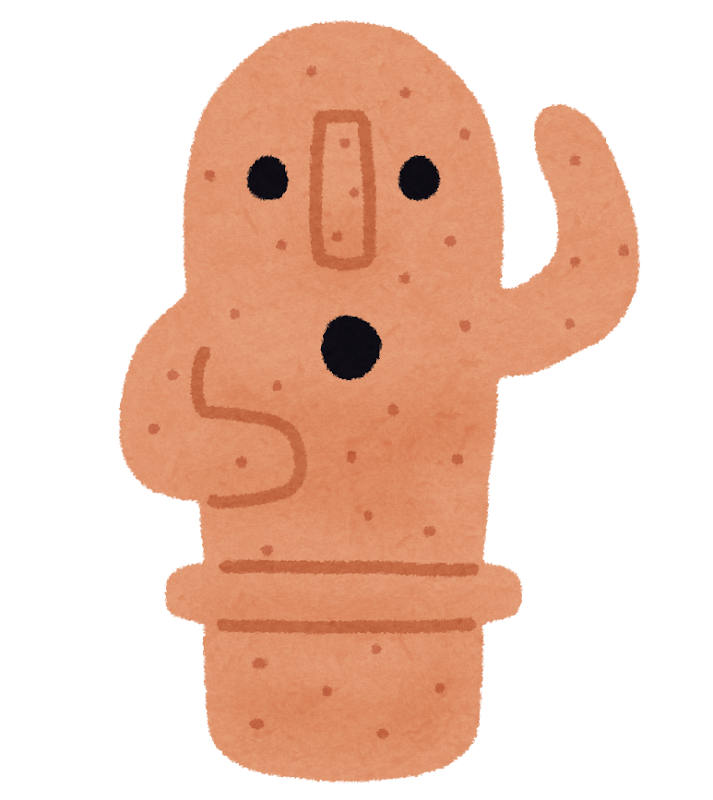盛況のうちに終了しました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。(2025.8.29追記)


毎回ご好評いただいている特別講座を、8月に夏期特別講座として開講します。今回のテーマは「食と健康の日本文学史」です。
以下、詳細をご確認ください。会員外の方も参加可能です。ぜひお誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください。
【日時】 8月28日(木)13:30~16:30(※13:00受付開始、座席および入退場自由)
【会場】 八王子市学園都市センター(八王子オクトーレ(旧八王子東急スクエア)12階)
第1セミナー室(定員60名)
【聴講料】1,000円(全部合わせて)※事前申込制。先着順に受け付けます。
【聴講料のお支払い方法】
聴講をご希望の方は、8月25日(月)までに下記口座に受講料1,000円をお振り込みください。お振込み確認後、メールあるいは電話にてお申し込み完了のご連絡をいたします。
当日の現金払いでの参加も受け付けますが、定員に達し次第打ち切りといたします。
【お振込み先】
郵便局振替口座 00100-4-487701 八王子文芸アカデミー
※手数料はご負担ください。なるべく、通信欄にメールアドレスをご記入ください。
※お申し込み後、キャンセルなさる場合は、必ず事務局までご連絡ください。
※当日の現金払いの場合はお釣りの出ないようにしてください。
【タイムスケジュール】
13:30~13:35 八王子文芸アカデミーの紹介
13:35~13:50 猫は見た!120年前の都市生活者の「食と健康」(深津謙一郎)
13:50~14:05 辛螺(からにし)で一杯(遠藤耕太郎・生駒桃子)
14:05~14:20 『万葉集』に描かれた食(岡部隆志)
休憩(10分)
14:30~14:45 『源氏物語』常夏巻の食事風景(岡田ひろみ)
14:45~15:00 平安時代 貴族のダイエット飯・庶民の妊婦食(菅野扶美)
15:00~15:15 いっこく玉子のつくり方(内田保廣)
15:15~15:30 人魚、雷獣、コレラ獣 ―妖怪食と薬食い―(今井秀和)
休憩(10分)
15:40~15:55 泉鏡花・食のこだわり、病の恐れ(富永真樹)
15:55~16:10 食に関わる語について(半沢幹一)
16:10~16:25 シェイクスピアを味わう(入江和生)
16:25~16:30 2025年度後期講座の紹介
【要旨】
猫は見た!120年前の都市生活者の「食と健康」/深津 謙一郎(元共立女子大学文芸学部教授)
漱石の『吾輩は猫である』。冒頭の一文は知っているけれども、最後まで読み通したという方は意外と少ないのではないでしょうか。今回は、猫が見た明治時代後期の都市生活者の「食と健康」をめぐる話題を切り口に、この小説の面白さの一端を紹介します。
辛螺で一杯/遠藤 耕太郎(共立女子大学文芸学部教授)・生駒 桃子(文芸学部非常勤講師)
『常陸国風土記』には、奈良時代の茨城県の特産物が記録されており、その中に「辛螺」という小さな巻貝があります。また『古事記』にはお酒を勧める歌とお礼の歌が出てきます。辛螺料理で一杯やる作法を伝授します。
『万葉集』に描かれた食/岡部 隆志(共立女子短期大学名誉教授)
万葉集にはいくつかの食物や調味料が詠み込まれています。それらを通して万葉の時代の食文化を知ることができますが、それらは和食の起源でもあり日本人の健康を維持してきたものです。その一部を紹介してみます。
『源氏物語』常夏巻の食事風景/岡田 ひろみ(共立女子大学文芸学部教授)
常夏巻冒頭には『源氏物語』には珍しく、調理や食事風景が描かれています。平安貴族の食文化を紹介しつつ、巻冒頭に〈食〉が描かれる意味も考えたいと思います。
平安時代 貴族のダイエット飯・庶民の妊婦食/菅野 扶美(共立女子短期大学名誉教授)
『宇治拾遺物語』に三条中納言朝成のダイエット話があります。医師に水飯を勧められ、実行したものの一向痩せない。はて?夏向きのメニューが並びます。つわりを歌った今様も一首。妊婦は何を食べたがったのでしょうか。
いっこく玉子のつくり方/内田 保廣(共立女子大学名誉教授)
人情本は幕末の“いき”な生活を描こうとしたジャンルです。その中に出て来る手作りファストフードです。簡単にできます。鰹節、お酒、玉子。そしてちょっと風邪気味ですねている芸者と若旦那が必要です。できれば長火鉢も。
人魚、雷獣、コレラ獣 ―妖怪食と薬食い―/今井 秀和(共立女子大学文芸学部准教授)
日本の古典を紐解くと、人魚を食べると不老不死になるといった記述が散見されます。江戸時代には「薬食い」(獣肉食)の果てに、雷獣やコレラ獣といった妖怪までもが俎板の上に。妖怪食から「食と健康」を考えます。
泉鏡花・食のこだわり、病の恐れ/富永 真樹(共立女子大学文芸学部専任講師)
谷崎潤一郎や内田百閒はじめ美食家で知られる近代作家は数多いですが、食のこだわりでは泉鏡花も負けていません。しかし、その異様なこだわりは病への恐れから生まれたものでした。そんな鏡花の「食と健康」へのまなざしを探ります。
食に関わる語について/半沢 幹一(共立女子大学名誉教授)
「たべる」と「くう」と「くらう」、ことばの基本的な意味はどれも似たようものですが、それぞれどのように違うのでしょうか。また、各語の由来はどのようなものでしょうか。知ってるようで、意外と知らない、ことばの小ネタを紹介します。
シェイクスピアを味わう/入江 和生(共立女子大学名誉教授・元学長)
シェイクスピアの作品には食べ物や飲み物への言及がたくさんあります。そこでシェイクスピアと飲食物との関わりについて考えてみたいと思います。結局、食べ物に強い関心がある人は、人間としてとても魅力的なんですね。あ、もう結論を言ってしまいました。